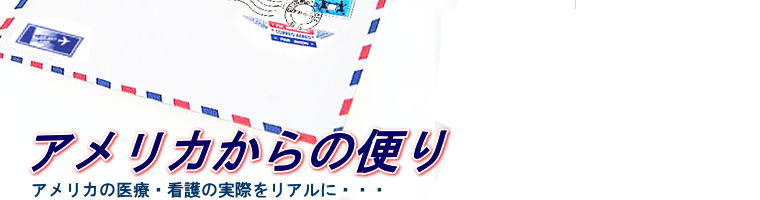
お久しぶりです。アメリカからの便りを更新するのがだいぶ遅くなってしまいました。
早くも2008年も9月にさしかかろうとしています。この9ヶ月間に、大イベントが3つありました。
1つは、翻訳を担当した看護研究のテキストが刊行されたことです。論文の翻訳の経験はあるものの、テキストの翻訳は初めてで、思いのほか、時間がかかり大変でした。現在、日本語の看護研究の本といえば、初歩的なものか、かなり高度なものかのどちらになり、詳しいながらも使いやすいテキストとなるとなかなかないため、このテキストの重要性を感じました。翻訳の際には、言語の複雑さにも直面しました。例えば、看護研究批評の際に利用される特有の言葉(History,maturationなど)は、状況や使用方法によっては意味が違ってくるので、翻訳の方法としては、適当な日本語を探し出して当てはめるのか、もしくはそのままカタカナを使ったほうが、ニュアンスが伝わり、正確な理解につながるのか、迷うことが多くありました。また、言葉は年代と共に変化するものでもあるので、どの用語が日本で一般的になっているのか、それを理解するのにも時間がとられました。例えば、10年前はエスノグラヒフィー(民俗学)といってもピンとくる人が少なかったのに大して、今では「エスノ」と略語で利用されているのを知り、言葉の浸透ぶりに驚きました。今年の6月に帰国した際、東京医科歯科大学の学生さん達と看護学の大学院教育についてセミナーを行ったのですが、日本では、アメリカのように系統だった授業形式ではなく、自力で看護研究を学ぶことが主流であることを知り、改めてこのテキストの重要性を感じました。(このテキストは中山書店刊「実践に活かす看護研究」。私は6・8・9章を担当しました。)
2番目のイベントは、6月をもって、博士課程1年目が終了したことです!1年目を乗り切る人のほとんどが卒業できると言われているので、その意義は大きいです。博士課程を1年経て実感していることの一つは、「研究」・「科学」という共通言語を学ぶことで学問間の垣根が低くなったことです。実際、他の学科の生徒と受講する授業も多く、博士論文作成においては、看護学だけでなく、保健衛生学、医学、疫学、社会学などの領域の先生方からアドバイスを受けることが推奨されてます。次年度は、量的研究方法、また疫学をより深く学ぶようになります。また、研究や教職における実践力をつけるために、研究や教育実習も行う予定です。
3番目で、もっとも最近の話題ですが、8月17日、私はサンフランシスコで日本語の流暢なアメリカ人と結婚しました(!)。このことについては、尽きることなく話せるのですが、それは別の機会にして、ちょっと変わったところで、サービスという観点でお話したいと思います。
日米を行き来するたびに、サービスの差を実感するのですが、結婚式の準備においてもこの差は顕著でした。どちらがいいとは簡単に評価できないのですが(それでも私は日本的サービスの方がありがたい)、私なりの解釈としては、日本は完成度の追求の意識が非常に高い。例外的なことへのサービス順応性が低い。サービス提供者の格差が少なく、サービスのレベルが均一である。安請け合いしない。時間通り。対して、アメリカでは、個性を尊重することが重要であり、「完璧さよりも不備があれば直せばいい」の精神。結果、例外には比較的大らかに対応する半面、サービス提供者の個人差が著しいです。よく気がつき、丁寧で愛想がいい人がいれば、携帯で長々とおしゃべりながらサービスを提供する無神経な人もいます。また、安請け合いや約束にルーズなことは多いです。
結婚式にあたっても、この方程式は当てはまりました。、アメリカでは、個性の尊重から、式場側が考える「いい式(完璧な式)」が押し付けられるのではなく、自分達の好みにアレンジできます。自由に企画できる反面、このプレッシャーは実に大きいです。私たちの場合は、エクセルを大活用し、分刻みの計画を練り、友人や家族にも手伝いをしてもらいました。それでも、色々な業者とのやり取りは本当に大変でした。。。日本みたいにパッケージだったらどれだけ楽か。。。何度もそう思いました。私は1年以上もかけて、この結婚式の準備をしてきたので、結婚式当日は、結婚する喜びに加えて、準備からの開放感でいっぱいでした。家族や友人に囲まれて、素敵な場所で、最愛の人と結ばれるのは本当に幸せなことでした。両親は、アメリカ式の式で、どうなるか心配していたようですが、心がこもったいい式だったと言ってくれました。
。。。さて、今は結婚式も終わり、仕事にも復帰(3週間もお休みを頂くことができました!)、新学期に向けて準備を開始です。次回の「アメリカからの便り」では、新学期の様子をご報告します!

喜吉 紘子 (看護師、保健師)
1977年10月生れ、10〜14歳までをアメリカで過ごす。
聖路加看護大学を卒業の後、およそ3年間虎の門病院に勤務。
カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)大学院にて修士号取得(看護管理学)。
現在、UCSF大学病院・治験病棟にて臨床看護師を務める傍ら、病院の看護研究/教育部の助手として も関わりを持つ。
今後の時代を睨み(株)メディカル・ コンシェルジュのアドバイザリー・ナースとしても活躍中である。
尚、喜吉紘子さんは2007年9月よりUCSFの博士課程に進学致しました。
1977年10月生れ、10〜14歳までをアメリカで過ごす。
聖路加看護大学を卒業の後、およそ3年間虎の門病院に勤務。
カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)大学院にて修士号取得(看護管理学)。
現在、UCSF大学病院・治験病棟にて臨床看護師を務める傍ら、病院の看護研究/教育部の助手として も関わりを持つ。
今後の時代を睨み(株)メディカル・ コンシェルジュのアドバイザリー・ナースとしても活躍中である。
「アメリカからの便り」
開設にあたって・・・
この度『アメリカからの便り』を開設するにあたって、病棟勤務、看護研究、翻訳業務などにて多忙を極める喜吉紘子さんに快くご協力頂きましたことを感謝いたします。
医療・看護に携わる全国の医療従事者の皆様方に向けて、今後の参考と励ましになれば嬉しく思います。
尚、喜吉紘子さんは2007年9月よりUCSFの博士課程に進学致しました。
| MC-ドクターズネット |
MC-ナースネット |
MC-薬剤師のお仕事 | 【MC-介護のお仕事】
会社案内 | 医療総合情報が満載のメディカル・コンシェルジュネット | 医学生のための情報サイト【医者たま.net】 Copyright c 2010 Medical Concierge all rights reserved. |