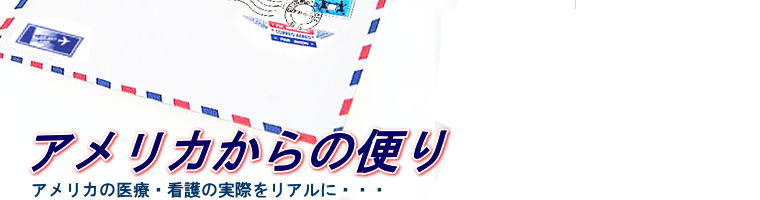
4月病
4月!
皆さんは、4月と聞いて、ワクワクして色々チャレンジしたくなるタイプでしょうか?それとも、最初の反応は「あ〜大変」?私はどちらかというと後者でしたが、前者の人もいると聞いてびっくり。その人は自分のことを「4月病」と表現していました。「5月病」はあるけど、なるほどと感心。確かに、新しい顔、新しい環境、ワクワクしてもおかしくないですよね。
皆さんは、4月と聞いて、ワクワクして色々チャレンジしたくなるタイプでしょうか?それとも、最初の反応は「あ〜大変」?私はどちらかというと後者でしたが、前者の人もいると聞いてびっくり。その人は自分のことを「4月病」と表現していました。「5月病」はあるけど、なるほどと感心。確かに、新しい顔、新しい環境、ワクワクしてもおかしくないですよね。
4月。思い出してみれば、病院勤務時代の4月は大変でしたね。新人の時は、緊張の毎日でした。朝、寝坊しないように。そんな基本的なところから。「先輩」になってからは、指導で忙しくて。
アメリカでは、新学期は8-9月です(4期制か2期制によって変わります)。医療現場では、新人医師が働き始めるのは6月です。これを受けて、皮肉の多い同僚は、「なるべく6月に医療機関にかかるのは避けるようにしている」と、言っていました。これはまた極端ですが、確かにUCSF大学病院の6月は、混乱が多く、簡単な処置や処方でも時間がかかる時期です。私は「誰にでも、学び始めの時期があるのだから、気長に待つことも必要」と思っても、忙しい時には、ついつい「早く!」と思ってしまいます。反省。(注:新人看護師は、UCSFでは年に4回ぐらい採用時期があるので、大勢の新人が一斉に臨床の場にでるということは少ないです。オリエンテーションの機会が多くて大変ですが、病棟的にはいいかもしれませんね。)
けれども、仕事の年数もたってくると、この4月(もしくは)6月「混乱状況」を先読みするようになります。私のストラテジーは、まず新人さんに(職種を問わず)「質問してもOK」とのメッセージを伝えておきます。医療の現場で何が一番怖いかといえば、あいまいな知識で医療処置を行ってしまうこと。自分の新人体験からでも思い当たります。コミュニケーションは大事です。後になって「びっくり」がないように、前もって話しておくことが重要です。
新人の学びの第1歩は「なにが分からないと分かること」。
ソクラテスのいう「無知の知」ということですね。新人時代、思い返してみれば膨大な情報と緊張の中で、易パニック状態でした(「易」感染者に似せての表現です)。もちろん、分からないことを減らしていくことは重要ですが、最初から全部分かるというのは無理です。
ソクラテスのいう「無知の知」ということですね。新人時代、思い返してみれば膨大な情報と緊張の中で、易パニック状態でした(「易」感染者に似せての表現です)。もちろん、分からないことを減らしていくことは重要ですが、最初から全部分かるというのは無理です。
そして、学びの第2歩は、自分の成長を認めてあげること。
もちろん、謙虚な姿勢で情報を吸収するのに必要ですが、学んでいることを認めてあげることも重要!留学したばかりの頃でも、英語が全然駄目だーと思うことは何度もありましたが、でも先学期よりは英語が出やすくなっているな、と自分を認めてあげることで少し元気がでました。
もちろん、謙虚な姿勢で情報を吸収するのに必要ですが、学んでいることを認めてあげることも重要!留学したばかりの頃でも、英語が全然駄目だーと思うことは何度もありましたが、でも先学期よりは英語が出やすくなっているな、と自分を認めてあげることで少し元気がでました。
新しい責任、環境。ワクワクするか、気が重くなるか。
気持ちによる部分も大きいですね。
皆さんの、4月にはワクワクが多いことを願ってます。
気持ちによる部分も大きいですね。
皆さんの、4月にはワクワクが多いことを願ってます。

喜吉 紘子 (看護師、保健師)
1977年10月生れ、10〜14歳までをアメリカで過ごす。
聖路加看護大学を卒業の後、およそ3年間虎の門病院に勤務。
カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)大学院にて修士号取得(看護管理学)。
現在、UCSF大学病院・治験病棟にて臨床看護師を務める傍ら、病院の看護研究/教育部の助手として も関わりを持つ。
今後の時代を睨み(株)メディカル・ コンシェルジュのアドバイザリー・ナースとしても活躍中である。
尚、喜吉紘子さんは2007年9月よりUCSFの博士課程に進学致しました。
1977年10月生れ、10〜14歳までをアメリカで過ごす。
聖路加看護大学を卒業の後、およそ3年間虎の門病院に勤務。
カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)大学院にて修士号取得(看護管理学)。
現在、UCSF大学病院・治験病棟にて臨床看護師を務める傍ら、病院の看護研究/教育部の助手として も関わりを持つ。
今後の時代を睨み(株)メディカル・ コンシェルジュのアドバイザリー・ナースとしても活躍中である。
「アメリカからの便り」
開設にあたって・・・
この度『アメリカからの便り』を開設するにあたって、病棟勤務、看護研究、翻訳業務などにて多忙を極める喜吉紘子さんに快くご協力頂きましたことを感謝いたします。
医療・看護に携わる全国の医療従事者の皆様方に向けて、今後の参考と励ましになれば嬉しく思います。
尚、喜吉紘子さんは2007年9月よりUCSFの博士課程に進学致しました。
| MC-ドクターズネット |
MC-ナースネット |
MC-薬剤師のお仕事 | 【MC-介護のお仕事】
会社案内 | 医療総合情報が満載のメディカル・コンシェルジュネット | 医学生のための情報サイト【医者たま.net】 Copyright c 2010 Medical Concierge all rights reserved. |