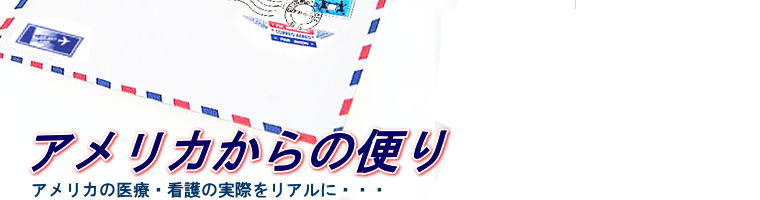
日本おける外国人労働者
昨日、Japan Society of Northern California主催の別府先生(スタンフォード大学名誉教授)による「日本における外国人労働者について」の講演に参加してきました。

英語で日本のことの講義を受けていてちょっと変な感じでしたが、勉強になりました。

英語で日本のことの講義を受けていてちょっと変な感じでしたが、勉強になりました。
意外とアジア人は少なかったです。半数いるかいないか。別府先生は、ロスアンジェルス生まれで、幼少期を日本で過ごし、17歳で米国に戻ったそうです。その際、両国の違いを目の当たりして、以後日本の研究をなされているそうです。
私は、日・フィリピン経済連携協定に基づくフィリピン人看護師・介護福祉士
候補者の受入れの動向に興味があって参加しました。
厚生労働省のホームページによると、当初2年間で看護400人、介護600人を上限として受け入れが予定されたようです。候補者は、自己負担で日本語研修費用、生活費を負担し、日本語検定試験にパスをし、更に日本の看護師・介護福祉士の試験に合格しなければなりません。研修を終えても試験に合格しなければ意味がありません。
フィリピン人の看護師はアメリカには非常に多いです。英語が話せることが有利ですね。私にも仲のいいフィリピン人の友人(同じくUCSF博士課程に在中)がいます。
彼いわくフィリピン人の看護師の収入が圧倒的に違うため、アメリカに移住する人が多いそうです。彼もその1人でした。アメリカの病院の人事部が直接フィリピンに行くこともあるらしいです。フィリピンで就職リクルート・移住の支援をする会社もあるくらいです。それに比べると、日本の医療現場で働くハードルは高いですね。毎日新聞(9月18日)によると、候補者の壮行会が18日にマニラ首都圏ケソン市で行われたそうですが、候補者は定員の50人を下回る30人だったそうです。日本への移住・研修の経済的負担が大きな理由だったそうです。
講演会の資料であった2006年外務省の出入国管理統計年報によると、登録されている外国人医療関係者はたったの173人。最も大きい職業項目は、国際業務に分類されるもの(約13万人)。他は、技術者が約7万人、エンタテイメント系が約5万人、投資・経営が4万人。芸術家でさえ約1000人が登録されているのに... 医療関係者は少ないですね。
私自身、外国人看護師としてアメリカの病院で働いています。そして、この機会を本当にありがたく思っています。言葉、文化は違っても(患者さんは平気でスリッパも履かず靴下のままで廊下を歩く。病院食にポテトチップスが出てくる!などなど)、想像以上に看護の知識や技術は通用します。
病院にもよりますが、外国人看護師(アメリカ以外で最初の看護資格を得た人)、1-3割を占めるでしょう。もちろん、外国人看護師にはそれなりの苦労はありますが、うまく機能しています。外国人看護師の努力と、病院側の受け入れ体制が重要です。例えば、今月のUCSF大学病院の看護総集会では、Diversity(多様化)が話題です。文化・言葉を乗り越えてどのようにチームとして医療を提供していくか、話し合われる予定です。
日本人看護師は、外国人看護師の割合としては少ないです(ブログなどの様子をみていると増えているようですが)。やまり発音がハードルになりやすい点はありますが、患者さんの受け入れはよく、他の看護師からももっぱら「丁寧」「細かい所に気づく」「もれがない」ということで、評判がいいです...
日本の医療も、新しい風が吹いてくれたらと思ってやみません。

喜吉 紘子 (看護師、保健師)
1977年10月生れ、10〜14歳までをアメリカで過ごす。
聖路加看護大学を卒業の後、およそ3年間虎の門病院に勤務。
カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)大学院にて修士号取得(看護管理学)。
現在、UCSF大学病院・治験病棟にて臨床看護師を務める傍ら、病院の看護研究/教育部の助手として も関わりを持つ。
今後の時代を睨み(株)メディカル・ コンシェルジュのアドバイザリー・ナースとしても活躍中である。
尚、喜吉紘子さんは2007年9月よりUCSFの博士課程に進学致しました。
1977年10月生れ、10〜14歳までをアメリカで過ごす。
聖路加看護大学を卒業の後、およそ3年間虎の門病院に勤務。
カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)大学院にて修士号取得(看護管理学)。
現在、UCSF大学病院・治験病棟にて臨床看護師を務める傍ら、病院の看護研究/教育部の助手として も関わりを持つ。
今後の時代を睨み(株)メディカル・ コンシェルジュのアドバイザリー・ナースとしても活躍中である。
「アメリカからの便り」
開設にあたって・・・
この度『アメリカからの便り』を開設するにあたって、病棟勤務、看護研究、翻訳業務などにて多忙を極める喜吉紘子さんに快くご協力頂きましたことを感謝いたします。
医療・看護に携わる全国の医療従事者の皆様方に向けて、今後の参考と励ましになれば嬉しく思います。
尚、喜吉紘子さんは2007年9月よりUCSFの博士課程に進学致しました。
| MC-ドクターズネット |
MC-ナースネット |
MC-薬剤師のお仕事 | 【MC-介護のお仕事】
会社案内 | 医療総合情報が満載のメディカル・コンシェルジュネット | 医学生のための情報サイト【医者たま.net】 Copyright c 2010 Medical Concierge all rights reserved. |