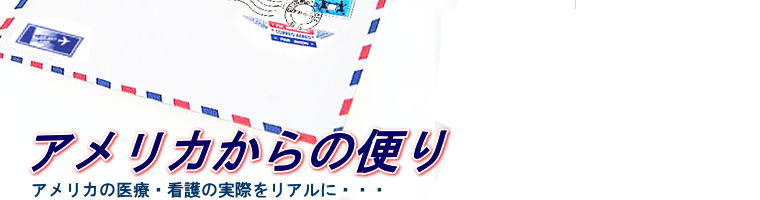
看護博士課程の生活:その1

ここに見えてるのは太平洋です。
サンフランシスコは晴れた日の空が大変美しい。
最近いい天気が続いて気持ちのいいサンフランシスコです。
6月に越す先のミシガン州は零下が続いていると思うと、
短パンでジョッギングに出れるのがうれしくなります。
6月に越す先のミシガン州は零下が続いていると思うと、
短パンでジョッギングに出れるのがうれしくなります。

ここに見えてるのは太平洋です。
サンフランシスコは晴れた日の空が大変美しい。
看護の博士課程というとアメリカ人でもびっくりする人が多いのですが、
今回は博士課程の学生がどのように過ごしているかご紹介したいと思います。
今回は博士課程の学生がどのように過ごしているかご紹介したいと思います。
UCSF看護学部博士課程の最初の2年は講義・セミナーが主です。週に14時間ほどの授業があります。仕事を続けながら学位取得を目指す人が多いので、授業は火曜日―水曜日(木曜日)の日中に集中しています。私も週24時間働くという契約で臨床看護の仕事を続けていたので、例えば火曜と水曜は授業、金曜−日曜は仕事ということをしていました。
ただ私の場合それは長続きはせず、次の学期からは仕事を週16時間程度と減らしました。ただ、残念だったのは、週24時間以上働くと、職場学割があり、授業料が1/3(!)となったのですが、尋常な生活をするためには妥協が必要でした。
さて、博士課程。何をしているかといえば、研究者の卵を育てます。で、研究とはなに?研究とは、真実を追求することです。真実というとなにか大げさに聞こえますが、要は「実際、どうなんだろう?」を探求することです。なので、博士課程ではまず好奇心とそれを追求するためのがんばり、そして研究するためのスキルが必要になります。
看護研究は量的研究と質的研究に大きく分けることができます。簡単にいえば、量的研究は数字を使う研究、例えば血糖値と日々の運動量の関係など。方法としては、この場合は採血と運動量を把握するためのアンケートなど。質的研究は、数字を使わず、言葉の分析によって物事の本質を理解しようとするものです。例えば複数のインタビューから得た情報から、単語やテーマを分析することで、延命治療に関する患者家族の懸念を理解するなど。私は、数字的に「答え」が出てくるほうが自分に合うので、量的研究をしています。日本の看護界では、量的より質的研究が最近は盛んなようです。日本の看護師さんは、患者さんの体験を理解しようという姿勢が強いからかな、と私は思ってます。
私は2009年の秋から博士研究に取り組んでます。まず、100ページほどの研究案を書き上げ、論文委員会の審査を受けます。OKをもらいましたら、実践の準備です。私の場合、アンケート調査だったので、アンケートの「最終調整」をしました。科学は知識の積み重ねなので、アンケートであってもなるべく他の研究者が作成し、アンケートとして信頼性・妥当性があるものを活用します。このように既存の知識に頼って「最終調整」であっても、結局私のアンケートが出来上がったのは4ヵ月後。その間、病院で研究をするための申請があります。これがまた大変で、ただのアンケート研究であっても70ページ近い資料を提出し、色々質問に答えて、これも4ヶ月かかりました。(余談ですが、病院によっては審査のために、高いと40万円ぐらいの費用を請求することもあります。私はラッキーなことにUCSFの学生であることから、どの病院の費用も免除になりました)。
そして、晴れてデータ収集〜!
次回は波乱万丈のデータ収集のお話です。
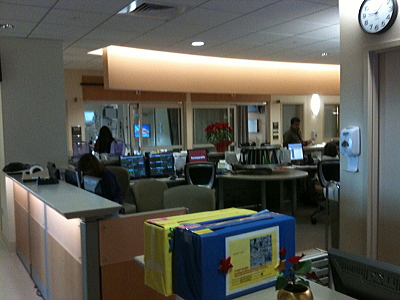
次回は波乱万丈のデータ収集のお話です。
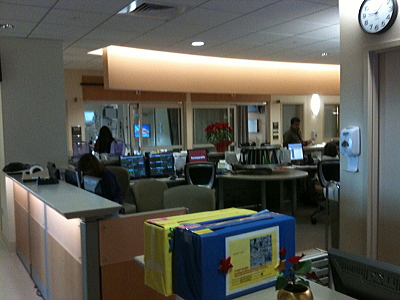

喜吉 紘子 (看護師、保健師)
1977年10月生れ、10〜14歳までをアメリカで過ごす。
聖路加看護大学を卒業の後、およそ3年間虎の門病院に勤務。
カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)大学院にて修士号取得(看護管理学)。
現在、UCSF大学病院・治験病棟にて臨床看護師を務める傍ら、病院の看護研究/教育部の助手として も関わりを持つ。
(株)メディカル・ コンシェルジュのアドバイザリー・ナースとしても活躍中。
尚、喜吉紘子さんは2007年9月よりUCSFの博士課程に進学致しました。
1977年10月生れ、10〜14歳までをアメリカで過ごす。
聖路加看護大学を卒業の後、およそ3年間虎の門病院に勤務。
カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)大学院にて修士号取得(看護管理学)。
現在、UCSF大学病院・治験病棟にて臨床看護師を務める傍ら、病院の看護研究/教育部の助手として も関わりを持つ。
(株)メディカル・ コンシェルジュのアドバイザリー・ナースとしても活躍中。
「アメリカからの便り」
開設にあたって・・・
この度『アメリカからの便り』を開設するにあたって、病棟勤務、看護研究、翻訳業務などにて多忙を極める喜吉紘子さんに快くご協力頂きましたことを感謝いたします。
医療・看護に携わる全国の医療従事者の皆様方に向けて、今後の参考と励ましになれば嬉しく思います。
尚、喜吉紘子さんは2007年9月よりUCSFの博士課程に進学致しました。
| MC-ドクターズネット |
MC-ナースネット |
MC-薬剤師のお仕事 | 【MC-介護のお仕事】
会社案内 | 医療総合情報が満載のメディカル・コンシェルジュネット | 医学生のための情報サイト【医者たま.net】 Copyright c 2010 Medical Concierge all rights reserved. |